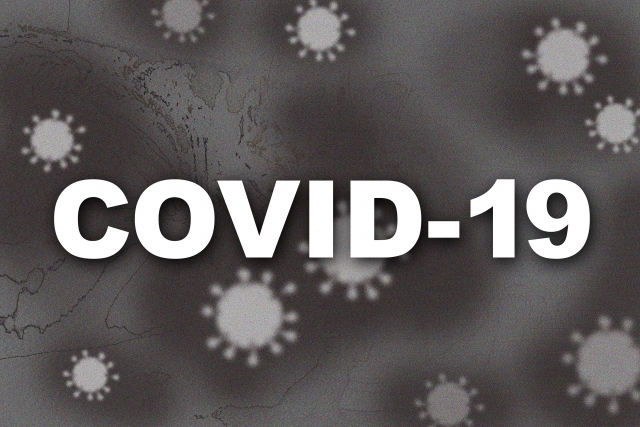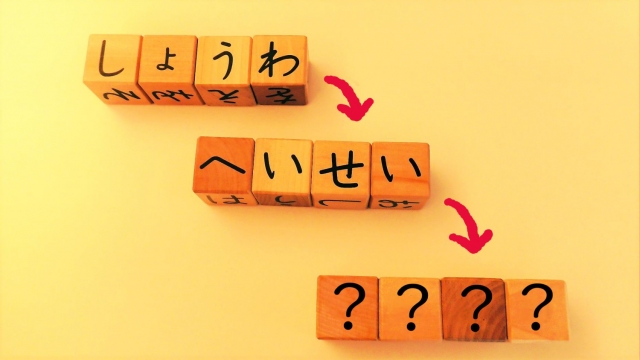
次の年号(元号)は何だと思う?
と、誰もが一度は話題に挙げていることでしょう。
企業が予想アンケートを取ったり、SNSで予想合戦があったり、東大生がガチ予想したりと生前退位だからこその盛り上がりですが、果たしてどんな年号(元号)となるのでしょうか。
予想はしませんが、年号(元号)について調べてみました。
いつ公表? 年号(元号)とは? 年号一覧、年号の決め方、年号の出典(由来)は? など書いていきます。
新年号は4月1日公表
新天皇即位が5月1日なので、新しい年号(元号)を即位の1カ月前には公表して、5月からは新しい年号(元号)が国民に周知されるようにしたいということでしょう。
それとともに、役所などの書類やさまざまなものを変更しなければなりませんよね。
果たして1カ月で間に合うのかどうか。
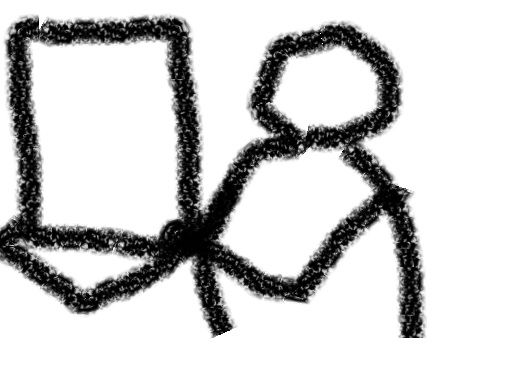
年号(元号)とは
年号とは「年につける称号」のことで漢字を使って表します。
元号は年号に似ていますが「即位の年から数える」ものであり、微妙に違うようです。
元号の元は元年の元ということなのです。
とはいうものの、広辞苑やwikipediaなどでは年号=元号となっていますから、どちらも同じ意味として使ってよさそうですね。

年号一覧
では、今までどんな年号(元号)があったのでしょうか。
これまでの日本の年号(元号)一覧を調べてみました。
あまりにも多いので、別のページに記載する予定です。
ここには明治天皇の時代からの年号(元号)を載せます。
| 漢字 | 読み | 頭文字 | 始 | 終 | 年数 | 天皇 | 改元理由 |
| 明治 | めいじ | M | 1868年1月25日 | 1912年7月29日 | 45年 | 明治天皇 | 明治天皇即位による |
| 大正 | たいしょう | T | 1912年7月30日 | 1926年12月24日 | 15年 | 大正天皇 | 大正天皇践祚による |
| 昭和 | しょうわ | S | 1926年12月25日 | 1989年1月7日 | 64年 | 昭和天皇 | 昭和天皇践祚による |
| 平成 | へいせい | H | 1989年1月8日 | 2019年4月30日(予定) | 31年 | 今上天皇 | 今上天皇即位による |
| (未定) | 2019年5月1日(予定) | 天皇名未定 | 生前皇位移譲に伴う |
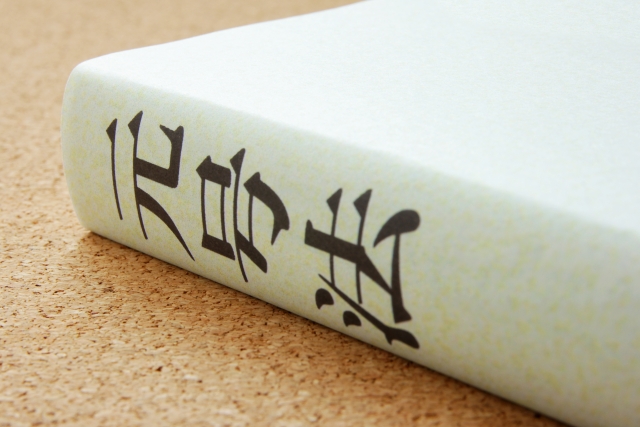
年号(元号)の決め方
中国の前漢第7代の皇帝である武帝から使用されはじめ、近隣国でも使われるようになっていった年号(元号)ですが、現在使っているのは日本だけなのだとか。
日本も昭和の後は西暦だけにしてもよいのでは?という政党もあった一方、世論調査をすると元号存続派が80%にもなったそうです。
それほど年号(元号)が一般的に使われているということなのでしょう。
西暦では味気なく感じるというだけではなく、4桁の数字よりも2桁のほうがわかりやすいという側面もあるのではないでしょうか。
西暦でも2桁に略すことがありますしね。
さて、年号(元号)は元号法という政令によって決められます。
元号法
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。
法律第四十三号(昭五四・六・一二)
つまり「皇位の継承があったら年号(元号)を改めましょう」ということなんだと思います。
明治天皇が「天皇一代に元号一つ」とする一世一元の制を定めた詔を発する前は「めでたい雲を見た」とか「白い亀をもらった」とか「天変、飢饉などの災害があった」ということをきっかけに年号(元号)を改めていたので、1年や数年で年号(元号)が変わることも少なからずあったようです。
それもなんだかいいような気がするのは私だけでしょうか。
ところで、元号法とともに、元号選定の具体的な要領も定めているようです。
- 国民の理想としてふさわしいようなよい意味を持つものであること。
- 漢字2字であること。
- 書きやすいこと。
- 読みやすいこと。
- これまでに元号又はおくり名として用いられたものでないこと。
- 俗用されているものでないこと。
ということで、年号(元号)は「過去に使われたことのなくて、人名や地名、商品の名前や企業名でなく、読みやすくて書きやすくて漢字2文字でよい意味を持つもの」であると限定されました。

判別しやすい文字・アルファベットであってほしい
「過去に使われたことのなくて、人名や地名、商品の名前や企業名でなく、読みやすくて書きやすくて漢字2文字でよい意味を持つもの」
ということで、かなり限定されているのではないかと思いますが、さらに、
- 略した時の頭文字が他の年号と判別しやすいもの
- 判別しやすいアルファベットであること
ということも考慮されるのではないでしょうか。
さまざまな書類で生年月日などの日付けを書くときに「明・大・昭・平」や「M・T・S・H」などに丸印をつけた覚えがあると思います。
それが「大・昭・平・照」だったり「T・S・H・N」だったりすると間違えてしまう可能性も捨てきれませんよね。
そのあたりもしっかり考えてくれるのではないかと思います。
ですから、少なくとも頭文字がM・T・S・H以外であることは確かでしょう。
「安久」ではなさそう
「安」という字を入れるのでは?との予想が多いそうです。
そのほかにも「平和」「和平」なども挙げられています。
しかし、残念ながら「俗用されているものでないこと」ということで、人名や企業名は選ばれることはなさそうです。
「平和」「和平」ももちろん熟語として成り立っている言葉なので候補の対象にはなりませんが、「安久」も潜水艦長に安久榮太郎(あんきゅう えいたろう)さんというかたがいたようで、人名なのですね。
そのため、書きやすく読みやすくても選ばれることはなさそうです。
それに、最近の年号(元号)の由来となる書物の一つ「易経」に「安」という字はあまり書かれていませんので、「安」がつく年号(元号)は難しいかもしれませんね。
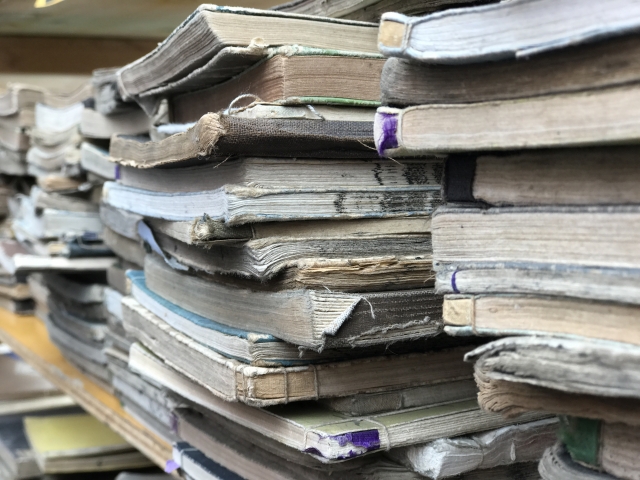
年号の出典(由来)
年号(元号)は出典が明らかでないといけないようです。
ということは、どの書物のどの部分から選んだのかがわかるということでもあります。
平成から明治まで新しい順に年号の出典(由来)をみてみましょう。
平成
『史記』五帝本紀の「内平外成(内平かに外成る)」、『書経(偽古文尚書)』大禹謨の「地平天成(地平かに天成る)」からで「国の内外、天地とも平和が達成される」という意味
wikipedia平成
昭和
四書五経の一つ書経堯典の「百姓昭明、協和萬邦」(百姓(ひゃくせい)昭明にして、萬邦(ばんぽう)を協和す)による。漢学者・吉田増蔵の考案。なお、江戸時代に全く同一の出典で、明和の元号が制定されている(「百姓昭明、協和萬邦」)。国民の平和および世界各国の共存繁栄を願う意味
wikipedia昭和
大正
『易経』彖伝・臨卦の「大亨以正、天之道也」(大いに亨(とほ)りて以て正しきは、天の道なり)から
wikipedia大正
明治
『易経』の「聖人南面而聴天下、嚮明而治」より。
「聖人南面して天下を聴き、明に嚮(むか)ひて治む」というこの言葉は、過去の改元の際に江戸時代だけで8回、計10回候補として勘案されているが、通算11度目にして採用された。岩倉具視が松平慶永に命じ、菅原家から上がった佳なる勘文を籤にして、宮中賢所で天皇が自ら抽選した。聖人が北極星のように顔を南に向けてとどまることを知れば、天下は明るい方向に向かって治まるという意味
wikipedia明治
4つの年号(元号)の出典をみると、史記や四書五経であることがわかります。
すでに政府は漢籍に詳しい学者の方々に委嘱しているそうですから、やはり今回も古い中国の書物から選ばれそうですね。
しかも、候補に挙げる年号の意味、典拠などの説明をつけなくてはいけないそうですから、「なんとなく」では済まされないでしょう。
史記や四書五経を読みこんでいる方であればもしかしたら予想できるかもしれませんよ。
ちなみに四書は「大学」「中庸」「論語」「孟子」、五経は「詩経」「書経」「礼記」「易経」「春秋」のことです。

予想が当たると違う年号になってしまう?
大正の次の年号(元号)が光文に決定したという誤報を東京日日新聞(現在の毎日新聞)が号外で流してしまったということがありました。
これは宮内省の情報が漏洩してしまったために、本当は光文と決定した年号(元号)を急遽、昭和に変更したのだそうです。
まさか、一般人がネットで予想合戦を繰り広げたからといってネット上での有力候補が外されるというわけではないと思いますが、あまり白熱するとどうなるかわかりませんよね。
予想、楽しいのですけど。